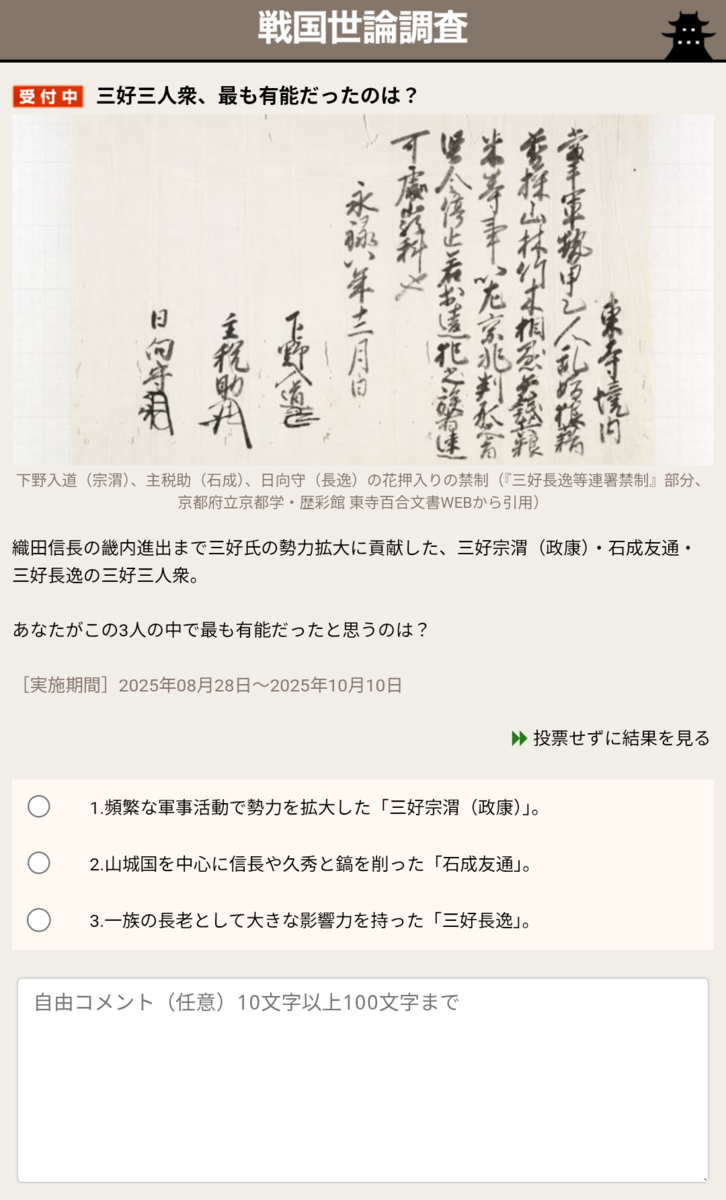戦国時代の経済・経営史を取りまとめた本が出版されていてかんたんしました。
こういう本が私は大好き。一般的な戦国時代の書籍は武将たちの軌跡を取り扱ったものになりますので行政や戦や組織運営や外交が重点的に語られますけれども、商業、農業、文化・芸能、あるいは宗教等、せっかくその時代に関心を持っているのだから世界観の幅を広げてくれる栄養を積極的に摂取していきたいところなのです。
↓少し詳しい内容紹介

中央権力が衰退し秩序と自由がせめぎ合う乱世を
あの手この手で乗りこなす――
天下は銭で回ってる中央権力が衰退し混迷する戦国時代、旧来の秩序を破る新興商人を、権力者たちは取り締まることが困難になった。新旧商人の縄張り争い、金融業の出現、拠点都市の建設、利権ビジネスと借金トラブル、御用商人の暗躍、世界貿易への参入、「楽市・楽座」の実態――。幕府、朝廷、大名、寺社、海外勢力、様々なプレイヤーが乱立する時代に、商人たちは何を頼り、秩序と自由の狭間を生き延びたのか? 史料に現れる、余りに人間的なエピソードの数々から、乱世を生き延びる戦略を学ぶ。
概要は上記引用の通りですが、オフィシャルHPで目次を詳細に教えてくださっていますのでそちらも引用させていただきます。
『商人の戦国時代』目次
プロローグ──戦国時代の商人とはどういう存在だったのか?
商人たちの訴え/戦国時代の利権ビジネス/中央権力の衰退で揺らぐ秩序/実は流動的だった「商人」という身分/中世商人はどこから来たのか?/特権を与えられた商人たち/「座」の盛衰第1章 戦国金融道 ──京都商人の栄枯盛衰
戦国時代のサービス業/様々な職人と売り子たち/船で運ばれた商品たち/塩の戦国時代/中世最大級の淀魚市/大坂湾を掌握した三好氏/塩の利権をめぐる争い/戦乱の時代の樹木需要/京都にはすべてが集まる/室町幕府のぜいたく三昧/戦国金融道――金融業者の登場/戦国時代の利子はどれくらいだったのか?/ついに不満が爆発する/比叡山延暦寺の抵抗活動/権門経営は守護代にアウトソーシング/幕府財政に関わった「野洲井」/野洲井と賀茂社との密接な関係/悪銭混入という社会問題/悪銭とは何か?/金融業者たちが躍動した京都/天皇家の資金管理を担った商人/土倉とは何か?第2章 ほんとうの「楽市・楽座」──兵庫・堺・博多・伊勢大湊
流通拠点での商業/瀬戸内海運の重要湾口都市「兵庫」/アジアとの貿易港「堺」/大名権力の支配下へ/「講」による自治/戦国時代の堺商人たち/「納屋」の正体/堺商人の家から大名になった小西行長/茶の湯と鉄炮を広めた堺商人たち/信長・秀吉と堺の関係/武家勢力による博多争奪戦/日本を代表する貿易窓口の盛衰/伊勢神宮の外港から太平洋海運の重要拠点へ「伊勢大湊」/角屋と北条・徳川家のつながり/そう単純ではない「楽市・楽座」/復興策・特権排除・治安維持/軍事戦略としての「楽市」/有名な織田信長「楽市・楽座」の実態/豊臣秀吉による「楽座」の完成第3章 新興商人vs.特権商人 ──利権だらけの中世
「特権商人」対「新興商人」――新旧商人の競合/四府駕輿丁座の形成/巨大な特権商人集団の誕生/米の権益を独占した駕輿丁座/米商人への統制/四府駕輿丁座の弱体化/既得権益を揺るがす新興商人集団/利権の張り巡らされた中世/偽文書による紛争決着/偽文書が通ったのはなぜか?/相互不干渉と先例主義/今度は通行権を争う/商売は実績が物を言う/意外な判決/保内商人の戦いは続く/枝村商人の反論/保内商人の再反論/保内商人の苦しい主張/証拠文書か実効支配か/六角氏による意外すぎる判決/斎藤道三の台頭/判決には裏がある!/癒着の決定的証拠か/戦国時代に賄賂は当たり前/木綿運送をめぐるさらなるトラブル第4章 御用商人たちの暗躍 ──商人的活動を担った大名家臣
石見銀は誰が運んだのか?/「銀山屋敷」と尼子氏の御用商人/毛利氏商人的家臣/交通の要衝「赤間関」の支配/返礼使として来日した宋希璟/瀬戸内海の水先案内人「東西の海賊」/宣教師ルイス・フロイスが遭遇した海賊/大名に仕えた因島村上氏/公権力から距離を置いた能島村上氏/大内氏がこだわった瀬戸内海/漂流物は誰の物か?/戦国大名と癒着した商人/キーワードは「商人司」/織田信長の商人司「伊藤宗十郎」/今川氏の商人頭「友野氏」/中央集権体制の消滅/伊勢神宮の布教活動/遍歴する修験者と商人第5章 大名たちの経営戦略 ── 「資源大国」日本
軍事力を維持するために必要なもの/衣服をめぐる経済学/苧麻を独占した「苧座」―― 越後長尾氏/特権にしがみつく手管/滞った特権収入/そして特権は別の手に移ってゆく/実は資源が豊富だった戦国時代/武田信玄の金山開発/上杉謙信の金山開発/世界的規模を誇った石見銀山/銀山をめぐる戦い/誰が銀山を支配したのか?/戦国時代の城下町/越前朝倉氏の城下町「一乗谷」/地方都市には珍しく医師が住んでいた/朝倉氏による商業の統制/北海道の物流拠点「勝山館」/アイヌと和人の交易/大分土着守護の城郭都市「大友氏館」/南蛮貿易とキリスト教/権力は秤の規格を決める/硫黄・火薬・鉄炮第6章 世界史の中の戦国時代 ── 貿易を担った商人たち
戦国時代はグローバル化の時代だった/石見銀山で世界に参入/多国籍化する東アジア/「倭寇的状況」―― 治安の悪化と貿易/倭寇討伐と日本への渡航禁止/堺商人が主導した日明貿易/細川と大内、遣明船同士の武力衝突/博多と堺、遣明船派遣合戦/貿易の中心を担った堺商人「日比屋了珪」/謎に満ちた経歴/南蛮貿易=東南アジアを介した貿易/今井宗久と堺の貿易/京都の名商人「角倉吉田氏」/角倉了以の南蛮貿易/豊臣政権の貿易統制エピローグ──新旧の秩序がせめぎ合った戦国時代
秩序と自由のせめぎ合い/自由から鎖国へ
どうです、この地域や業種の網羅性!!
詳しい人であれば目次を眺めてピンとくる案件も多いと思います。各地の戦国時代大名研究の文脈で取り上げられるような経済トピックスを、こんなんにも大集合させて総観させてくれるとアガりますよね。
地域という視点では、この手の武将以外本は畿内を無視、逆に畿内(京や堺)のことしか書いていない、のどちらかになりがちですけれどもこの本に限ってそういう心配はございません。細川家や三好家などのややマイナー気味な大名勢力圏も、各地のメジャーな大名勢力圏も、ばっちり模様が記されております。三好ファンや堺ファンにももちろんおすすめですよ。
しいて言えば瀬戸内海関係以外の四国がちょっと寂しいくらいでしょうか。四国の中世・戦国時代研究がもっと注目・投資されてほしいぜ。
業種や事業活動という視点でも、農地管理(荘園)、金融、業界団体による政治交渉、鉱山経営、海運および海外交易、大名御用商人、地域公共財への投資等々、様々な事例が紹介されますので読んでいて飽きません。
滋賀県の某地域の新興商人衆が偽文書を活用して勝訴しまくっていた事例が取り上げられるなど、プリミティブでパッションあふれる経営活動っぷりを堪能できるのが読みどころ。戦国時代は商売であれ武術や芸能であれ「道」が体系化・一般言語化される以前の時代ですので、ふつうのビジネスパーソンがそのまま朝礼やスピーチのネタにとり入れられるような逸話は少ない※のですけれども、秩序が再構築される過程の混沌期にあってがむしゃらに生存・発展を図っていくバイタリティ、知恵の絞り出しや飛び込む勇気や司法行政・宗教団体との癒着折衝といった経営上のセンスはばっちりインプット可能です。歴史好きのビジネスパーソンにはもちろんおすすめですよ。
※とはいえ「正直屋」という商人が存在したくらいですので、商売する上で「正直が大事」という価値観自体は当時から存在したのでしょう
本の内容からは少し離れますが、巻末に著者さんも「ビジネスパーソンって歴史本けっこう好きだよね」と書いてくれていましたので雑感を。
たしかに経営者って歴史や古典が好きな人が多くて、従来から戦国時代のウンチク本であったり歴史小説や歴史ゲームであったりを通じて有名な逸話(真偽は問わない)を学び、そのことを判断力の涵養に活かしてきたという文脈は存在すると思います。
有名な逸話、真偽は問わない、という点では史学を学ぶ人にとって残念なことではあるのですけれども、有名な逸話=人の情緒に訴えるところが大きいですので、「人間を知る」「感情の動きを知る」「間を学ぶ」等の点でロールプレイ・ケーススタディ的な研鑽効果も実際あるのでしょう。
軽い内容の雑学本や楽しい歴史コンテンツはとっつきやすいですしね。
一方、この10年くらいでかなり増加した一次史料ベースのちゃんとした研究を一般人に教えてくださる系の書籍群、この読者層にもけっこうビジネスパーソンって含まれている感覚があります。研究者や学生、クリエイター、土地の人々等のしっかり研究したい方々だけでなくて、ビジネスパーソン的な一般人も買い支えているからこその盛り上がりに映っているんですよね。
学術的な研究成果についても、史実ベースということはすなわち良質なドキュメンタリーであるわけですから、「英雄的個人の逸話」ではないぶん分かりにくいところはありつつも、確かな説得力、「人間とはこういう行動を取るもの」「こういう行動にはこういう結果が伴うもの」ということを学ぶにはとてもよい事例集なのであります。歴史小説とはまた違う角度ではありますが、やはり判断力を伸ばすという点では有意義なのでありましょう。大げさに言えば基礎研究の成果が社会で役立っている! です。
たぶん当書籍の読者層は、先に戦国時代研究が好きで、そこから周辺的世界として商業史にまでスコープを広げていく、的な方が多いと思います。
でも、今でも茶道や武道のルーツを知りたくて戦国時代に詳しくなる人もいることですし、これから商業史の研究・周知が進めばそこから入って戦国時代に興味を持つ人も出てくることでしょう。そのためにも、このように良質な研究成果を集約したような本が出てくれることは大歓迎ですし、未来は明るいと感じ取れて嬉しくなるものですね。
商業史にかぎらず、その時点の研究成果を広く集約したような本が好きです。
あまり出ていないジャンルであればなおさら!
こういった良著をベースに、研究や注目がますます進展していきますように。