江戸時代の伊勢神宮参りを舞台にした人々の意識の建前と実態を興味深い筆致で描いた本が出版されていてかんたんしました。
なかなかデリケートな話題・論点をふんだんに含みますのでていねいに本を読むタイプの人以外には勧めにくいところもありますけれど、著者の視点は穏やかで現実肯定的な感じがしますので私的には読後感よかったです。
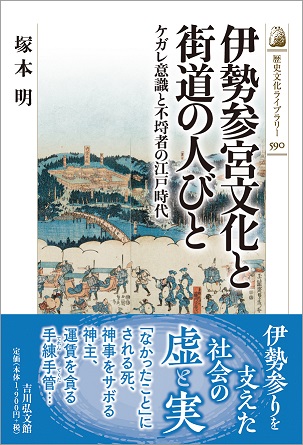
江戸時代、多くの参宮客で賑わった伊勢。神宮領ではケガレを避け、清浄さが求められたが、その実態はいかなるものだったのか。ケガレを避ける方策、神主の人事と勤務実態、街道沿いでの商売、恋物語と女性たちの人生…。厳粛性の裏に世俗性・卑俗性を持ち合わせた参宮文化と、伊勢に生きた人びとを活写。伊勢参りの舞台の、個性豊かな社会を描く。
伊勢の実像に迫る視角―プロローグ
参宮客と「ケガレ」の回避
参宮客を迎える芸能民
被差別民の参宮
仏教と参宮神宮領の「清浄さ」のしくみ
「死穢」の判定
「なかったこと」にされる死―速懸
動物のケガレの除去―犬狩御師の実態と参宮文化
御師と伊勢参宮
伊勢での案内と接待
不埒な参宮客と神主
神主の人事制度
神主の勤務実態と外部評価参宮街道沿いの人びと
御師と上方旅籠屋の客引き
街道の諸稼ぎ
参宮街道恋物語
愛と憎しみの人間模様伊勢が迎えた近代
「異国」の接近とケガレ意識
異国認識の諸相と維新期の転換伊勢の近代化の光と影―エピローグ
参考文献
あとがき
上記目次のとおり、神社ならではの「ケガレ」意識についての話題が続きますので、現代の差別問題に繋がっている点もあり、慎重な読解が必要かなと思います。
被差別民の存在、彼らと伊勢参りの関係等も史料に基づいて描写されていますが、建前として差別的な要素は江戸時代から確かに存在していたこと、実態的には被差別民も神宮へ参拝できるような柔軟な取扱い・共生模様があったこと、しかしながら幕末~明治期に建前的な差別要素を前面に押し出すような政策が一時取られたこともあって江戸時代のあり方と近代のあり方に一定の意識の隔絶が生まれてしまったこと、等が察せられるようになっています。
受け止め方はさまざま幅があるかもしれませんが、誰もがより生きやすい方向に受け止めてくれる読者が多いといいですね。
同様に、史料に基づいて神宮の暮らし模様が率直に描かれていますので、神宮の伝統や文化をからかうような方向に受け止める読者が出ないといいな、とも思います。
エピソードがシンプルに興味深いんですよね。
「死穢」が発生すると神宮の諸行事や観光客受入れがストップしてしまうので、神宮周辺で死者が発生しても「まだ死んでいません」という態にして墓まで運んで埋めてから「いま死にました」という処置をとったり。
神主さんたちも生活がけっこう苦しいので御師(伊勢参りのガイド)商売に精を出し、神事をサボりまくる人がけっこう存在したり。
なんというかいい意味でも悪い意味でも日本社会のコンプライアンス運用といいますか、建前は厳密で立派なんだけど運用面は抜け道だらけで現実に折り合いをつけている感じなのです。
いわゆる原理主義者的なマインドの人が読むと憤ってしまうかもしれません。
抜け道運用をなんでもOKOKやりまくると結局は大問題に繋がるのが現代社会ですのでううんと思う感じもあるのですが、そうはいってもこの本で描写される神宮周辺の方々は真剣に現実と折り合いをつける運用を模索しているのがよく分かりますので、ううんと思いながらちょっと応援もしたくなる、妙なあたたかみのある歴史紹介になっているんですよ。
不思議な歴史本だ。
著者さんの視点もそういう伊勢社会に対して懐深いのがいいの。
神宮という、日本文化の中でもトップクラスに格式的で伝統的っぽい場所を舞台に、理屈と現実のはざまでもがいてきた人々のありようをそのままのかたちで摂取できるという点で、含蓄のある本だなあと思いました。
この本を読んで、もっとルールどおり厳格にせねばと思う人もいるでしょうし、やっぱ建前だけじゃ通らないよねと思う人もいるでしょう。
けっこう人生観、社会観を試される本ですし、そういう意味で優れた歴史教材になっているのではないでしょうか。
理想の追求、現実との折り合い、不要な差別意識の解消等々、いずれも人の英知を以てますます良い世の中になっていきますように。